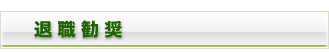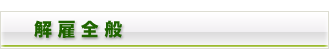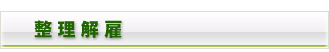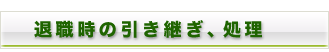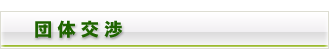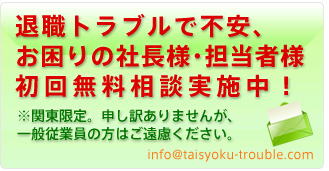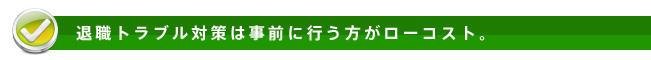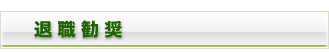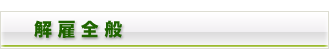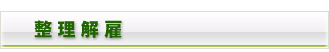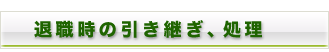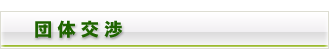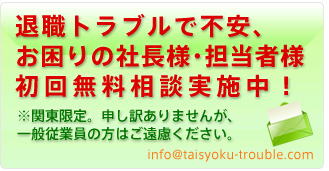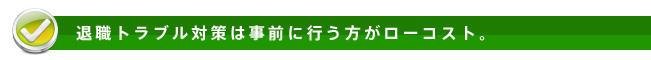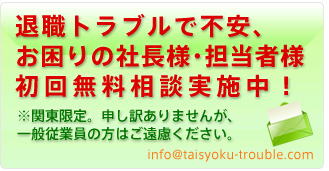
東京人事労務ファクトリー
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-13-5 BPRレジデンス渋谷1002
TEL : 03-5778-9817
(平日9:00~18:00)
※スマホの場合、電話番号をタッチすると
電話が掛かります
事務所のご案内はこちら |
|
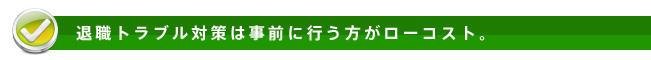
退職トラブルが発生してから、いざ対策を取ろうとしても、会社にできることは非常に限られています。
たとえば会社が解雇を行い、元社員が撤回を求めてきた場合、会社ができるのは相手に対し、「解雇は正しかった」と主張することのみです。
法的根拠を踏まえ、万全の準備をして行った解雇であれば、自信を持って対応できるかもしれませんが、そうでなければ相手の主張が認められ、会社にとって不利な結果となる可能性が非常に高くなります。
訴訟にせよ、組合との交渉にせよ、一度起こった事実を覆すことはできず、一度起こった事実以上の結果が出ることは無いのです。
退職トラブルにより会社が支払うコストを軽減するためには、事後の対応ではなく、日頃から就業規則など退職に関する正しいルールを持ち、正しく運用していくほかありません。
以下に当事務所でお勧めする今日からできる退職トラブル対策を挙げてみました。
就業規則の整備を軸に大技、小技を取り混ぜて載せています。
本やネットを参考にした就業規則をお使いの会社もあるかと思いますが、それらは必要な対策をフォローしていない可能性があり、また会社ごとの実情を反映して作られていません。いざという時に備え、トラブルの温床を一度、徹底的に点検しましょう。
① 退職の申し出(退職願)、解雇通知はそれぞれ書面に残す。
退職の申し出や解雇通知を口頭で済ませてしまっている会社は注意が必要です!
私の事務所へも退職トラブルに関する相談が寄せられますが、その中には「すでに退職した社員から、離職票に記載されている退職の理由などについてクレームをつけられた」といったものもあります。
退職者にとって、特に退職の理由は雇用保険の基本手当(失業給付)を受ける時期や退職金の額に関わってくるため、非常に重要なのです。
ひどいケースですと「そもそも退職を申し出た覚えはない」などと主張され、なかったことにされてしまう場合もあります。
会社のいうことが事実だったとしても、いざという時に証拠がなければ苦戦することになります。このようなトラブルを起こさないためには、退職の手続きをすべて書面で行うようにし、証拠として残しておくことが必要です。
② 就業規則または労働契約に解雇の要件を定める。
解雇をめぐり訴訟で争った結果としての判例では、解雇は就業規則や労働契約に定められた理由によるもののみ認め、それ以外は認められない傾向にあります。
解雇というのは社員にとって生活の基盤である仕事を奪われることです。何をしたら解雇となるのか前もってオープンにしておかないことにはあまりにアンフェアであり、可哀想だともいえます。
実務上でも解雇を行う場合には、就業規則または労働契約の定めにより、根拠を示して行うことになります。
まずは就業規則または労働契約に何をすれば解雇となるのか定め、社員に対し周知しましょう(周知の結果、解雇を行う必要がなくなれば何よりです)。
ちなみに、あまりに軽い行為では解雇とすることはできませんので、注意が必要です。
③ 日頃から社員の勤務状況に関する資料を残しておく。
いざ、社員を解雇しようとすると「なんとなく」で行うわけにはいかず、客観的な根拠が必要とされます。
勤務成績の悪さを理由とするならば、人事考課や指導録を、出勤状況の悪さを理由とするならば、出勤簿というようにです。
これらの資料があれば後で解雇の撤回を求められたとしても、根拠として示すことができます。社員の側にとってもフェアといえるでしょう。
給与改定等の参考としても使えるため、日頃から勤務状況に関する資料は整備しておくべきです。
なお、資料があっても実際に解雇に価するかの判定は非常に微妙であるため、解雇を行う際には専門家に相談されることをお勧めします。
④ 労働契約の更新条項を明確に定める。
契約社員や嘱託社員など、期間を定めて雇用する契約を何度も更新していると、更新を会社の都合だけで打ち切ること(雇い止め)が法的に難しくなってきます。
つまり、こうした法的措置には、弱い立場の社員側を保護する目的があり、契約の更新を重ねるほどに、この先もずっと契約更新が続いていくだろうとの期待感を高めてしまうことになる点に配慮がなされているというわけです。
ですから、そうした法律上の知識もなしに不用意に雇い止めを強行すると、後で雇い止めの無効を申し立てられて再契約せざるを得ない結果となってしまいます。
ただし、判例を参照するかぎりでは、契約社員にたいする雇い止めは、正社員の解雇より認められやすい傾向があります。
そのため、労働契約の更新を行う(行わない)条件をあらかじめ労働契約に定めておくことをお勧めします。次回の契約の更新を行わない場合に、契約書に明記されてあることで雇い止めがしやすくなるからです。
解雇と同様、細心の注意を要するところ ですので、契約の作成にあたっては専門家に相談されることをお勧めします。
⑤ 正社員とする前に試用期間を設ける。
試用期間中の場合はまた事情が変わってきます。一度雇い入れた社員を解雇することは非常に大変ですが、試用期間中であれば解雇や本採用の拒否が法的に認められやすい傾向にあります。
会社にも雇い入れた社員の仕事ぶりを通じて見極めるための時間が与えられているのです。
もちろん、働く側にとってもこの先、果たして自分に合った職場として働いていけるか、会社を総合的に判断する良い機会でしょう。
試用期間中の解雇や本採用の拒否は無制限に認められるわけではなく、就業規則および労働契約に試用期間を設ける旨を定め、正社員登用および解雇の条件を定めておく必要があります。
⑥ パート、アルバイトと正社員の違いを明確にする。
パート、アルバイトの就業規則や賃金規程について、正社員とは別に定めていない会社が多くありますが、正社員の規定をそのまま準用するのには注意が必要です。
なぜかといいますと、そうした就業規則や賃金規程の定め方ですと、そこで社員に支払うとされている賞与や退職金の規定が、そのままパートやアルバイトにまで適用され、支払われることになっているかのように見なされてしまう可能性があるのです!
そういうわけですので、パート、アルバイトの処遇については、労働契約書、パート就業規則などで、社員との違いを明確に定めておく必要があります。
⑦ 退職の手続きを明確に定める。
退職時の引き継ぎや有給休暇の消化などでトラブルが発生するケースがあります。
いずれも退職の申し出から退職日までの期間に余裕がなく、限られた対応しかできないことに原因があるようです。
退職までの期間に余裕を持っておくため、たとえば「退職を希望する場合は30日前までに会社に退職届を提出する」と就業規則および労働契約に定めておきましょう。
法的な拘束力はありませんが、社員に自覚を促す効果は期待できます。
退職金や賞与がある場合は退職時の手続き及び引き継ぎを行うことを支給の条件とするのも良いでしょう。
⑧ 保証人を付けておく。
私の事務所でも「社員と突然連絡が付かなくなった」と相談を頂くことがありますが、このような場合、会社が取れる対応は非常に限られています。
行っていた仕事を他の社員に引き継がねばなりませんし、会社の一存で退職扱いとするには後で異義を申し立てられるリスクがあります。
このような場合、本人以外の連絡先を事前に確保しておくことが重要です。
できれば入社時から保証人となってもらうことで、軽率な行動を行わないよう本人に自覚を促すことができます。
退職するにしても、保証人を通じて退職の意思を伝えてくるケースがあり、手続きがスムーズになります。
なお、保証人になってもらうためには身元保証書などの書式の準備が必要となります。
⑨ 休職制度を設ける。
プライベートのケガや病気で社員が長期に欠勤する場合、休職の扱いとしておくのが、会社の都合からすれば得策です 。
休職している期間は給与、賞与の支払いおよび退職金の計算の対象とはしません。
ただし、その期間にも会社は 社会保険料などのコストを支払わなければならないため、
一定期間職場に復帰できなかった場合、自動的に退職となるという出口を就業規則の中であらかじめ設けておくと 良いでしょう。
社員としてはケガや病気が治っていないのに退職というのは心細い感じがしますが、こうしておけば、制度だから仕方がないと一定の気持ちの整理が付くのです。
休職制度を設けるには、就業規則に定めを行っておく必要があります。
その際には必ず、事前に起こりうる諸々のケースを想定したうえで、明確な規定を設けておくことにより、社員に疑問の余地や不安、不満などを与えずに対応できるよう備えておく必要があります。
ここまで書いてきた通り、退職トラブル対策は事前に行ったほうが、圧倒的にローコストで済みます。
当事務所では日頃のメンテナンスも含め、これらの対策を一括してお手伝いしております。
リスクの有無の調査および改善のご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください!
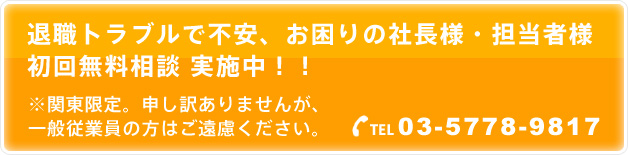
|
|