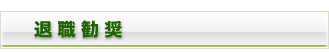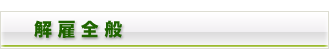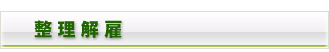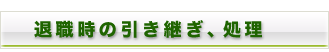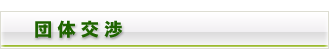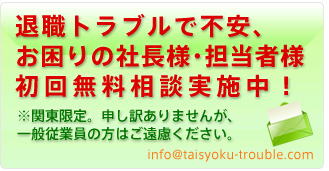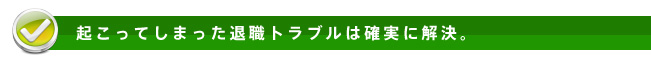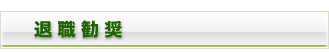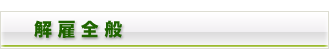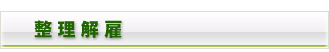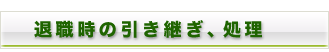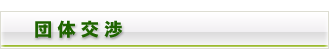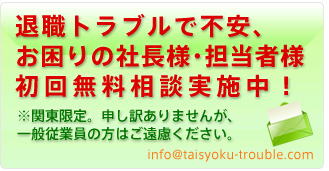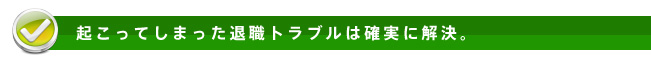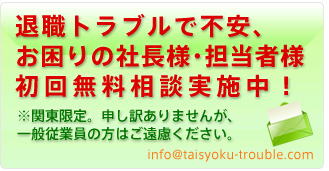
東京人事労務ファクトリー
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-13-5 BPRレジデンス渋谷1002
TEL : 03-5778-9817
(平日9:00~18:00)
※スマホの場合、電話番号をタッチすると
電話が掛かります
事務所のご案内はこちら |
|
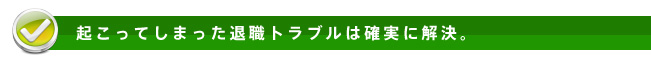
退職トラブルが起きた場合、事が退職というデリケートな問題だけに慌ててしまいがちです。 しかし、ここで問題をこじらせないためにも、まずは心を落ち着かせることが大切です。
そこから、適切な対応をするにあたり、いくつかチェックすべき点を以下に挙げてみます。
* 社員が退職に際し会社に不利益を与えているならば、回復は可能か。交渉するための材料があるのか。
* 会社が行った解雇に対し異義申し立てがあったならば、妥協の余地はあるのか。
* 異義申し立てに対し、会社側として交渉に時間を使うことができるのか。
それぞれの状況に会社側の考え方を加味して、取るべき対応を決定します。
基本的には社員がゴネ得を通すことを許してしまったり 、間違った対応を取って問題を大ごとに発展させるようなことは何としても避けねばなりません。
ここでは私のこれまでの経験から、トラブル解決へ向けたヒントをご紹介していきます。
■ トラブル発生時に、まず取るべき対応は?
① 社内ルールおよび諸法令を確認し、方向性を見極める。
退職トラブルが発生した場合、まずは就業規則や賃金規程、労働契約、および労働基準法などの諸法令を見直しましょう。会社および社員の主張、取った行為がルールに則しているかどうかを確認する必要があります。社員にルールを逸脱した行為があるのであれば、それを根拠に会社の意見を主張していきます。
解雇に対する異義申し立ての場合、会社がルールに則して解雇を行ったのであれば、その事実を主張します。
あるいは、会社の側にルール上の弱いところがあると見られる場合、ルールによる強制ではなく対等な立場での交渉を行う方向性を模索していくことになります。
② 突然、出社しなくなった社員への対応。
退職トラブルには事後の対応が難しいものもあります。
特に、既に退職した社員に会社の言うことを聞いてもらうのは困難です。
例えば、社員が必要な引き継ぎをせず、そのまま出社しなくなってしまったという悩ましいケースがあります。
他の社員の代替えが利けば良いのですが、そうはいかない仕事もあるでしょう。
この場合、悔しいところもありますが、会社は社員に「お願いして」来てもらうほか、取りうる手段はありません。
会社が持ち出す交渉材料としては、金銭かそれに準ずる休暇などが考えられます。退職金の割増などを条件に、引き継ぎを行うよう交渉を行っていきます。
突然、出社しなくなった社員についてはまず、当人と連絡を取らなければなりません。
当人がだめなら、保証人(家族)などに連絡を取ります。
連絡がついても、私の経験した所ではそのまま退職するという流れになることが多いのですが…。
どうしても連絡がつかない場合は退職(就業規則に定めがある場合)または解雇で処理します。
ここで、退職または解雇を法的に正当化するため、再三出勤を督促したというステップが必要となるのです。
③解雇に対し、異議申し立てがあった場合の対応。
会社が行った解雇に対し、元社員から異義の申し立てがあった場合はどう対応したらよいでしょうか。
解雇を行うというのは会社にとっても余程のことで、一度解雇した社員を復職させるという気分にはなかなかならないかと思います。
もちろん、余程自信を持って解雇をしたというのであれば、そのまま解雇の主張を曲げないことはできます。しかし、相手が労働組合や労働基準監督署へ相談に行き、会社に対して手間やコストを掛けることもなきにしもあらずです。最終的に争いの場が訴訟にまで至るリスクもあります。
そう考えてくると、なるべく解雇した社員との話し合いで決着を付けたいところです。
敢えて会社が解決金を支払うことで、退職の確定、社員は解決金の受け取りで妥協するという落としどころもあります。徹底的に争って白黒つけるよりもコストが安くつくのであれば、経済的なメリットもあるでしょう。
もちろん、解雇した社員のニーズによっては他の交渉材料を持ち出すケースもあります。
いずれにせよ、交渉の結果はしっかり書面に残しておきましょう。
そして、法的な不備のないように、専門家に相談されることをお勧めします。
■ 結局、問題解決はオーダーメイド。
このように退職トラブルとそれに対して取るべき対応は千差万別で、残念ながら一部の事例でしか解決のための 対処法をお伝えすることができません。
起こってしまった退職トラブルを解決するためには法的な根拠が前提となるほか、相手と交渉を行わなければなりません。
相手の意図を汲み取り、場合によっては妥協を図る方向に進めていきます。
当事務所では問題解決に向けたサポートを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
■労働組合(ユニオン)が団体交渉を申し入れてきた時には?
ある日突然、労働組合から会社に「団体交渉の申し入れ」が来たら、どのように対応を行うでしょうか?
実際に、社員が労働組合の力を借りて退職トラブルの交渉に当たってくる事例が頻発しています。
労働組合との交渉に慣れていない方が対応すると、海千山千のプロである相手方にやり込められる憂き目に遭い、意を決して行った解雇さえ早々に撤回するようにと、判断を迫られることになります。
解雇しようとした社員に言いたいこと、感情的に割り切れないところも多々あるでしょう。
しかし、労働者の味方として法的に理論武装をした労働組合を相手にして、感情論をぶつけたところでまったく通用しません。
それでけでなく、「忙しい社長を連日の電話でせかして煩わせる、街宣活動を行う」などと言って、手段を選ばず会社の嫌なところを突いてくるケースも出ています。
私もこれまでに多くの社長さんが労働組合との交渉でストレスを抱えているところを見てきました。
ストレスを逃れるためにと労働組合の言うことをそのまま受け入れてしまうのですが、それでは相手の思うツボ。主張すべき点については断固主張しなければなりません。
正しく対応すれば意外に簡単に解決できる場合もありますので、なるべく早く、「要求書」を渡されて、すぐに当事務所へご相談されることをお勧めします。
当事務所では団体交渉時の事前対応、団体交渉への同席を行い、会社側の意見を最大限主張致します。
労組対応で抱えたストレスが解消したと喜びの声も頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
■ 労働基準監督署から呼び出しがあった時には?
社員が退職トラブルについて問題を感じた場合、駆け込み寺として労働基準監督署へ相談に行くケースが多くあります。
残業代など周辺の取り扱いも含めた退職時の取り扱いを調べ上げ、問題が見つかった場合は、会社に対し呼び出しのうえ指導をしてきます。
労働基準監督署は平たく言えば、裁判所のような「証拠絶対主義」です。提出された資料をもとに法的に問題があれば、会社に対しどんどん改善を要求してきます。
また、労働基準監督署はある程度法違反が明確でないとアクションを起こしません。したがって、もし連絡があった場合は何らかの証拠をつかんでいると言っていいでしょう。
労働基準監督署から呼び出しがあった場合、会社側も就業規則や賃金規程など証拠の提出を要求されます。何も問題がなければいいのですが、問題が発覚すれば、修正するよう「是正勧告」が出されます。
一度出された勧告に従わなかった場合には、経営者が告発されることさえあるので、対応としては極力不利な勧告が出されないよう利用できる手元の資料をフルに活用し、会社側にとって有利な事実はどんどん主張していかなければなりません。
労働基準監督署の担当者も人間ですので、呼び出し時に取る対応によっては会社の意見を汲み取ってくれるような場合があります。一人で慌てて対応するのではなく、社会保険労務士など専門家を同席させることで、事がスムーズに運びます。
当事務所では呼び出し時の事前対応、同席、および是正勧告への対応を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
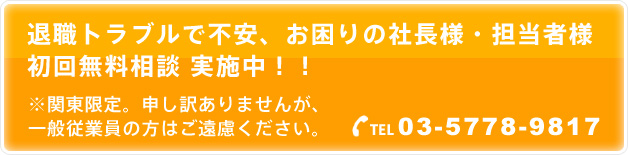
|
|