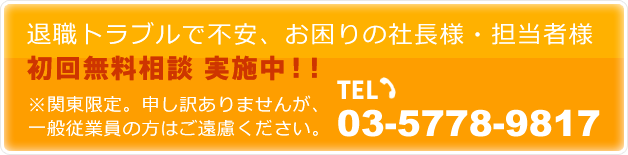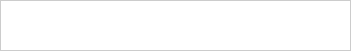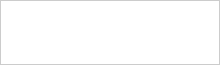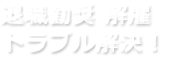1.退職証明書と解雇理由証明書を作成する際に注意すべきこととは。
① 退職証明書はセミオーダーメイド
退職日以降に従業員であった者が会社に請求してきた場合、会社は退職証明書を作成し、交付しなければなりません。退職証明書は労働基準法により交付が義務づけられている書類なのですが、決まった様式はなく、任意の書式に必要な事項を記載すればよいということになります。
退職証明書には以下のうち、従業員であった者が請求してきた事項のみを記載します。
・対象者の氏名
・使用期間
→ 入社日から退職日までの期間を記載する。
・従事していた業務の種類
→ 職種を記載する。例えば、システムエンジニア、経理事務、足場工など。
・その事業における地位(役職)
・賃金
→ 月給○○万円といった程度でよいが、基本給と諸手当や賞与を分けて書くこともできる。
・退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)
→ 一身上の都合、解雇、定年など。解雇の場合は「売上○○万円の横領が発覚したため、就業規則第○条による懲戒解雇」などと具体的に記載するが、本人が希望しない場合はこの部分の記載を省略しなければならない。
・会社名、代表者職氏名
任意の書式とはいえ、従業員であった方が請求していない事項については、上記にあっても記載することができず、会社としてはセミオーダーメイドに応じねばなりません。
② 解雇理由証明書は事実通り記載するようにする
解雇予告を行った従業員が退職日 までの間に請求してきた場合、会社は解雇理由証明書を作成し、交付しなければなりません。解雇理由証明書とは退職証明書の一種で、労働基準法により交付が 義務づけられている書類なのですが、決まった様式はなく、任意の書式に必要な事項を記載すればよいということになります。内容については退職証明書を簡略 化したものでして、その名の通り、ほぼ解雇理由さえ記載されていれば必要充分です。
解雇理由証明書には以下の事項のみを記載します。
・対象者の氏名
・解雇予告を行った日
・解雇理由(就業規則上の根拠と事実関係を含む)
→普通解雇、懲戒解雇、整理解雇など。就業規則上の根拠がある解雇の場合は「心身の故障により業務に
耐えないため、就業規則第○条による普通解雇」などと具体的に記載するが、本人が希望しない場合はこ
の部分の記載を省略しなければならない。
・会社名、代表者職氏名
少し待てばより情報が網羅された退職証明書が手に入るというのに、わざわざ在職中に解雇理由証明書を求めてくるというのは、会社に対して解雇の無効を訴えようとしているのか、なにやら自らの退職に納得できていない節があるともみられます。 後々、解雇理由証明書を弁護士やユニオンに証拠書類として持ち込まれる可能性もあるので、事実と異なる記載がないよう心がけねばなりません。
2.退職証明書、解雇理由証明書と上手に付き合う方法とは。
① 退職証明書、解雇理由証明書の交付を拒否できるケース
従業員(であった者)から退職証明書および解雇理由証明書の交付の請求があった場合、会社はその用途を問わず、これを拒んではならないこととされています。交付を行う義務のある期間は退職証明書の場合、退職日から2年経過するまで、解雇理由証明書の場合、解雇予告通知日から解雇日(その他の理由で退職した場合は退職日)までとなります。 交付を請求できる回数は決まっていないため、この期間内は何度でも応じないといけません(社会通念上相当と思われない回数の請求であれば応じなくて良いと思われます)。退職日から2年経過すれば、退職証明書の交付に応じる必要はありません。
ちなみに、退職時に雇用保険の離職票の交付を受ける際に、会社は「雇用保険被保険者離職証明書」という書類に証明を行っており、これには離職日と離職理由、離職前数ヶ月分の賃金額が記載されています。 そのため、離職証明書と重複する事項を改めて証明する必要はないと考えられそうですが、これは、離職者が雇用保険の失業給付を受給する目的にのみ利用される書類ですので、退職証明書や解雇理由証明書の交付に代えることはできません。
② 退職証明書を採用に活用する
退職証明書や解雇理由証明書を交付する側としては、その行方は気になるところです。退職をめぐるトラブルがあり、会社の責任を追及するために、弁護士やユニオンが背後で提出を求めているという場合はありますが、再就職先の会社において、選考または採用時に退職証明書の提出を求められている場合もあります。 退職証明書を交付する側には義務しかありませんが、一方、自社で社員を採用しようとする側としては、退職証明書の提出を義務づけることで、前職の経歴を確認することができる効用があります。採用の際に、求職者が提出してきた書類や申述をそのまま信用することも多いのですが、のちに経歴に「色を付けて」申告していたということも多く、トラブルになりがちです。そのため、本人を通じて前職の会社に依頼することで、使用期間、職種および地位、賃金、退職の理由まで照会することができ、採用時のミスマッチを防ぐことができます。
調査対策サービス
労働基準監督署調査対策 │ 年金事務所調査対策 │ 労働組合対策
手続代行サービス
労働保険・社会保険手続代行 │ 労働保険・社会保険新規適用 │ 助成金申請代行 │ 給与計算代行 │ 労災保険特別加入(中小事業主) │ 労災保険特別加入(一人親方)